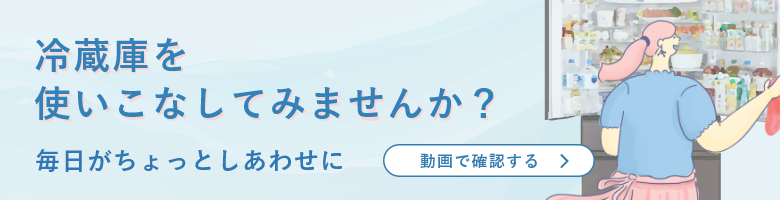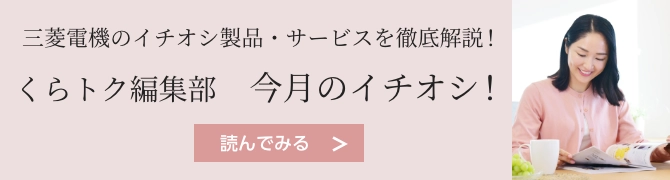【2025年版】大掃除のポイントは?事前準備や掃除場所&手順を三菱電機が徹底解説!

年末になると、ご自宅の大掃除に取りかかるのが定番ですよね。家族総出で時間をかけて行えば、一年の汚れを落として、すっきりとした気持ちで新年を迎えられるでしょう。とはいえ、ただでさえやることの多い年末。育児や仕事で時間を捻出できない方にとっては、家中の大掃除のために十分な時間を作るのも難しいかもしれません。
この記事では、日頃忙しく過ごしており、できるだけ効率的に大掃除を進めたい方に向けて、ポイントや手順などを解説します。
目次
大掃除前に準備するべきポイント4選1.事前にスケジュールを立てる2.チェックリストを作成する3.掃除道具を準備する4.廃棄物の分別ルールを確認しておく大掃除を効率よく進めるポイント2選1.午前中に大掃除をスタートする2.掃除の優先順位を決める【場所別】掃除方法を伝授!エアコンキッチンレンジフードファン(換気扇)冷蔵庫浴室洗濯機トイレ窓ガラス床・フローリングベランダ大掃除を行うときに忘れがちな場所5選天井と壁の隅窓のレール・サッシ冷蔵庫の裏家具の下や裏シンク下の収納大掃除後の清潔を保つための習慣化のコツ週ごとの掃除スケジュールを作成する1日5分の小掃除を取り入れる汚れが付く前に防止するアイテムを導入する収納を見直して整理整頓をキープする作業が難しい場合は業者の力を借りるまとめ:大掃除は計画的に行いましょう!大掃除前に準備するべきポイント4選
大掃除を始める前に、次の4つのポイントに沿って準備をしておきましょう。
以下で一つずつ解説します。
1.事前にスケジュールを立てる
まず、いきなり大掃除に取りかかるのではなく、事前に、どこをどのようにお掃除するかをある程度考え、スケジュールを立てておくことをオススメします。大掃除は無計画に始めてしてしまうと無駄な作業が増え、効率が悪くなってしまうこともあるからです。
大掃除のスケジュールは、以下2つのポイントに分けて作成するのが基本です。
1-1.掃除する場所をリストアップする
全ての場所をピカピカにお掃除できればそれに越したことはありませんが、実際には仕事や家事、育児などで忙しく、家中隅々までお掃除するのは困難というご家庭も多いでしょう。
限られた期間内で満足できる状態に仕上げるには「ここだけはどうしてもお掃除したい」という場所をピックアップし、優先的にスケジュールに盛り込んでいく必要があります。
具体的な手順として、「必ずお掃除する場所」と「余裕があればお掃除する場所」の2つに分けてリストアップしていきましょう。日頃あまりお掃除しない場所や、汚れやすい場所を含めるのがオススメです。
一例として、以下のような場所は大掃除する場所のリストに入れると良いでしょう。
- 窓ガラス・サッシ・網戸
- 換気扇・レンジフード
- キッチン
- 風呂場
- 床・壁・天井
- 玄関
- トイレ
- 洗面所
- カーテンレール
- 照明
- ベランダ・バルコニー
- 押し入れ・クローゼット
水回りは日頃からお掃除している方も多いですが、カビや水アカ、浴室の天井などは手が届きにくい場所です。この機会にしっかりお掃除しましょう。高い場所の汚れは見落としがちで、長期間放置すると頑固な汚れに変わります。脚立を使って、じっくり取り組むことが大切です。
1-2.各場所の掃除に必要な時間を見積もる
大掃除を一気に終わらせるのは大変なので、12月中旬あたりから数日に分けて行うことで、より楽に進めることができます。また、仕事や家事、育児などと並行して行う場合は、どの場所にどれくらいの時間をかけるかを大まかに見積もることが重要です。時間を見積もったら、平日と休日にそれぞれどのくらいの時間をかけるかを考えます。
週末にまとめてお掃除する場合は、無理なく進めるために1日2~3時間を目安にスケジュールを立てましょう。例えば、キッチン掃除を約2時間と見積もり、週末1日をキッチン掃除の日とする計画が考えられます。
平日も少しずつお掃除を進めたい場合は、場所を細かく分けてスケジュールを立てると良いでしょう。なお、場所だけでなく汚れ具合によっても所要時間は変わるため、特に汚れがひどい部分には多めに時間を見積もることをオススメします。家族と相談しながら、お掃除の担当を決めるとスムーズです。
2.チェックリストを作成する
スケジュールと合わせてチェックリストも作成しておくのが、大掃除を効率的に進めるポイントです。大掃除のチェックリストは次のような内容で作成します。
| 担当 | 日付 | 場所 |
|---|---|---|
| キッチン | ||
| 〇〇 | 〇月〇日 | レンジフードファン |
| 〇〇 | 〇月〇日 | シンク |
| お風呂場 | ||
| 〇〇 | 〇月〇日 | 鏡 |
| 〇〇 | 〇月〇日 | 浴槽 |
家族で大掃除をする場合、誰が・いつ・どこをお掃除したのかが分かるようにしておきましょう。例えば完了予定日を記入して、実際にお掃除が終わったら予定日に丸を付けるといったルールを決めておきます。
チェックリストを作成することで進捗が把握できるため、スケジュール通りに進んでいるかの確認が可能です。また、事前にお掃除する箇所をリストアップしておくことで、大掃除から漏れてしまう箇所をなくせます。
3.掃除道具を準備する

スケジュールを立てたら、必要なお掃除道具や洗剤を準備しましょう。大掃除では家中のあらゆる場所をお掃除するため、それぞれに適した道具や洗剤が必要です。
「いざ始めようと思ったら足りなかった……」とならないよう、事前に必要な物をリスト化し買い足しておきましょう。
年末の大掃除で活躍する主なお掃除道具と使い方のポイントは次の通りです。
| お掃除道具名 | 使い方のポイント |
|---|---|
| 掃除機 |
|
| ハンディワイパー |
|
| フローリングワイパー |
|
| クロス、スポンジ |
|
| ブラシ |
|
| スクイージー(水切りワイパー) |
|
| 粘着クリーナー |
|
| 新聞紙 |
|
特にクロスやスポンジ、ブラシ、ワイパーの替えなどは一度の大掃除につき複数個使用します。途中で足りなくならないよう、多めに準備しておきましょう。
また必須ではありませんが、上記の他に補助用として使い古しの歯ブラシや割り箸、つまようじも準備しておくと、ブラシやスポンジでは届かない細かな部分をお掃除するのに役立ちます。
続いて、年末の大掃除に必要な洗剤とそれぞれの特徴は以下の通りです。
| 洗剤の種類 | 特徴 |
|---|---|
| (弱)アルカリ性 |
|
| 中性 |
|
| (弱)酸性 |
|
洗剤は、日常的な汚れに幅広く使える中性洗剤が基本です。中性洗剤で落ちにくい皮脂汚れや水アカ、石鹸カスなどには酸性洗剤やアルカリ性洗剤を汚れごとに分けて使用することが有効ですが、素材によっては傷める恐れがあるため、使用前に取扱説明書を必ず確認してください。
特に酸性洗剤と塩素系洗剤は混ぜると有毒ガスが発生するため、同時使用は絶対に避けましょう。同じ場所で使う場合は、別の日に分けるか、十分に洗い流してから換気を行ってください。酸性洗剤の代わりにクエン酸、アルカリ性洗剤の代わりに重曹を使う方法もありますが、素材との相性には注意してください。
また、大掃除では比較的強い洗剤を使うことや水仕事が多くなるため、ゴム手袋は必需品です。換気扇のファンなど鋭利な部品をお掃除する際の怪我防止には軍手が便利ですし、ホコリの吸い込み防止にはマスク、高い場所のお掃除で目を保護するにはゴーグルもオススメです。
加えて、作業中は必ず換気を行いましょう。窓を開ける場合は、部屋の対角線上にある窓を開けて空気の通り道を作ると効果的です。ただし、高層階では突風の危険があるため、窓を開けずに換気扇を回すなど工夫してください。小さなお子さんやペットがいる場合は、網戸も忘れずに閉めておきましょう。
4.廃棄物の分別ルールを確認しておく

年末の大掃除で不用品を処分することがあります。普段から処分している紙や缶などであれば、分別に迷うことはないでしょう。しかし年末の大掃除では、電化製品や粗大ゴミのように頻繁には発生しない廃棄物が出る可能性があります。適切に処分するためにも、自治体の廃棄物の分別方法を確認しておきましょう。
一部の廃棄物は適切に分別しなければ、事故につながる恐れがあります。例えば、可燃ゴミにリチウムイオン電池を混ぜてしまうと、ゴミ収集中に火災が発生する可能性があり大変危険です。
廃棄物については分別だけでなく、回収のタイミングも確認しておきましょう。タイミングによっては年内のゴミ回収が終わってしまっている可能性があります。年内に処分できないと、年明けまでゴミを溜めておかなければなりません。
すっきりと年始を迎えるためにも、大掃除のスケジュールを立てる時点で、ゴミ回収のスケジュールまで考慮しておくのがオススメです。
大掃除を効率よく進めるポイント2選
大掃除を効率的に進める際は次のポイントを押さえておきましょう。
1.午前中に大掃除をスタートする
大掃除は、午前中に始めることで効率がぐんと上がります。午前は体力・集中力が高く、自然光を活用できるため汚れの見落としも少なくなります。特に冬場は日照時間が短いので、朝のうちから作業を始めることで、十分な明るさの中でお掃除を進められます。
また、午前のうちに水回りや換気扇など時間のかかる場所に着手すれば、洗剤をなじませている間に他のエリアを並行してお掃除でき、効率的です。窓拭きやベランダ掃除など、屋外作業も朝の時間帯は風が穏やかで作業しやすい傾向があります。
さらに、午前中に大掃除を終えることで午後は片付けや休憩に時間を使え、年末の忙しい時期でも心に余裕が生まれます。
2.掃除の優先順位を決める
大掃除はあちこち手当たり次第に行うよりも、優先順位を決めて取り組んだ方が効率的に進められます。
ここでは大掃除の優先順位の決め方と基本的な流れを5段階に分けて説明します。
2-1.訪問者が多い場所から掃除を始める
年末年始に家族や友人を迎える予定がある場合は、玄関・廊下・リビング・トイレなど、来客が多く滞在する場所からお掃除を始めましょう。
泊まり客がいる場合は、風呂・洗面所・ダイニングキッチン・寝室も対象にすると安心です。
エアコン内部のお掃除を検討している場合は、大掃除シーズンの繁忙期前に業者へ依頼するのがオススメです。内部部品のお掃除は故障や不具合を防ぐため必ず業者に任せましょう。
三菱電機の公式エアコンクリーニングがオススメ!
- ご自身ではお掃除できないエアコン内部を分解洗浄します。
- ニオイのもととなるカビやホコリをプロの技術で取り除きます。
- 電気代や効き具合に影響する内部汚れによる冷房効率の低下を改善します。
※サービス提供エリアに限ります。サービス詳細は下記リンクをご参照ください。
2-2.高い場所から低い場所へ順番に進める
ホコリは上から下に落ちるため、天井、照明、家具の上、床の順にお掃除を進めるのが基本です。窓を開けて換気する場合は、風向きを考慮して風上に当たる窓回りから開始すると良いでしょう。
また、棚や家具の上を拭く際は奥から手前へ動かし、ホコリを奥に押し込まないようにしましょう。
お掃除の順番に関しては以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
家の掃除は高いところから低いところへ!毎日の掃除を簡単にするポイントは?
2-3.大きな家具や家電を移動させて掃除する
チェストやソファー、テレビ、冷蔵庫などの裏や下は、ホコリやゴミが溜まりやすい場所です。隙間からお掃除するだけでは行き届かないため、できるだけ動かしてお掃除しましょう。
移動は2人以上で行い、家電は必ずプラグを抜いて安全を確保してください。冷蔵庫は短時間なら庫内温度の上昇は少ないですが、扉はしっかり閉めて作業を行いましょう。
設置場所だけでなく、家具や家電本体の背面・裏面もキレイにします。特に家電は静電気でホコリを吸着しやすいため、普段見えない部分ほど念入りに行いましょう。
2-4.キッチンや水回りは重点的に時間を確保する
キッチン・トイレ・風呂などの水回りは、家の中でも特に汚れやすく、頑固な汚れが多い場所です。水アカ・カビ・石鹸カス・油汚れなどが蓄積しやすいため、他の場所よりも多めの時間を確保しましょう。目安は以下の通りです。
- キッチン:1時間半~3時間程度
- トイレ:40分~1時間半程度
- 浴室:1時間~3時間
キッチンは水回りであると同時に火や油を使うため、油汚れと水アカが混ざった落ちにくい汚れが多いです。特に換気扇やレンジフードは分解・置き洗いなどで手間と時間がかかります。
トイレは面積が狭くても、天井・壁・床に加えてタンク内部や換気扇までお掃除する場合は時間を要します。尿石や黒ずみがある場合は洗剤の放置時間も必要です。
浴室は浴槽や浴槽エプロン、天井、換気扇、ドア回りなど、普段手を付けにくい場所が多く、一つひとつに時間がかかります。特に薬剤を浸透させる作業が必要な場合は、待ち時間も含めて計画に行いましょう。
キッチン・トイレ・浴室それぞれの掃除方法は、以下でも詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。
キッチンの掃除方法は?汚れの特徴やポイントを場所別に詳しく解説
トイレの床掃除を簡単に終わらせる方法を便利道具と一緒に紹介
お風呂掃除を徹底解説!汚れや場所に応じて適した洗剤・方法も紹介
2-5.最後に床やカーペットを掃除する
全てのお掃除が終わったら、最後に床を掃除機がけします。窓は閉めてホコリの舞い上がりを防ぎましょう。
フローリングは水拭きかウェットワイパーで仕上げ、カーペットは中性洗剤を薄めた水に雑巾を浸して固く絞り、優しく拭きます。 丸洗いできるカーペットは、掃除機をかけた後に家庭用洗濯機や浴槽で洗浄します。掃除機をかける前に洗うとゴミが繊維の奥に入り込むことがあるため、要注意です。
フローリング、カーペットの詳しい掃除方法は、以下のページでそれぞれご紹介しています。
汚れをキレイに!フローリングの正しい掃除方法について解説
カーペットはこまめに掃除しないとだめ?掃除の頻度や基本的な掃除方法、やってはいけないことを徹底解説
【場所別】掃除方法を伝授!
大掃除の要所となる、以下の場所のお掃除方法を紹介します。
エアコン

エアコン掃除の際は取扱説明書を確認し、安全のため運転停止と電源プラグの取り外しから始めます。
前面パネルやグリルは外せる場合は水洗いし、柔らかい布で拭いて陰干ししましょう。フィルターは外す前に掃除機で表面のホコリを吸い取り、汚れがひどければ中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、よく乾かします。
また熱交換器は軍手を着用して掃除機や毛ブラシを使い、優しくホコリを除去。吹出し口やフラップも水拭きし、汚れが強い場合は中性洗剤で優しく拭きましょう。
室外機も天板や裏側のホコリをブラシ付き掃除機で取り除きます。内部洗浄は誤った方法で故障や火災の恐れがあるため、市販洗浄剤の自己使用は避けてください。最悪の場合、発煙や発火につながる恐れがあり「独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)」が注意喚起を行っています。
■注意喚起動画(再現実験映像)エアコン「4.内部に洗浄液がかかりトラッキング現象で発火」
先述のように、エアコン内部の洗浄は高い専門知識が必要です。カビのニオイや内部汚れが気になる場合は必ず専門業者に依頼してください。
三菱電機でも、メーカー視点でのエアコンクリーニングサービスを提供しています。三菱電機製以外の製品にも対応しているので、お気軽にご相談ください。
また、エアコンのお手入れ方法については以下の記事でも詳しく解説しています。
エアコンのお手入れについて解説!必要な準備や実施の目安とは?
三菱電機の公式エアコンクリーニングがオススメ!
- ご自身ではお掃除できないエアコン内部を分解洗浄します。
- ニオイのもととなるカビやホコリをプロの技術で取り除きます。
- 電気代や効き具合に影響する内部汚れによる冷房効率の低下を改善します。
※サービス提供エリアに限ります。サービス詳細は下記リンクをご参照ください。
キッチン

キッチンはIHやガスコンロ、シンク、排水口などお掃除箇所が多いため、場所ごとにお掃除方法を変えましょう。
IHは必ず電源を切り、冷えてから作業します。軽い汚れは絞ったクロスで、油汚れは薄めた中性洗剤で拭き取ります。こびり付いた汚れはクリームクレンザーと丸めたラップでこすり、水拭きするのがオススメです。
ガスコンロは特に五徳(ゴトク)のしつこい油汚れが落としにくいため、重曹水で煮沸し、冷ましてからスポンジで洗うと効果的です。
排水口のぬめりは重曹を振りかけて数分後にこすり、ニオイが気になる場合は重曹を1〜2杯かけ熱湯を注ぎましょう。レンジフードや換気扇は部品を外してつけ置き洗いを行うと、油汚れが落ちやすくなります。
いずれも作業中はやけどや怪我に注意し、お掃除後はよく乾燥させてから元に戻しましょう。
キッチン掃除の方法の詳細は、以下でもご紹介しています。
キッチンの掃除方法は?汚れの特徴やポイントを場所別に詳しく解説
レンジフードファン(換気扇)

作業前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ります。ケガを防ぐために、軍手などの厚手の手袋を着用し、不安定な台に乗らないように注意しましょう。
レンジフードファンの油汚れには、中性洗剤が有効です。強くこすったり金属タワシを使ったりすると塗装が剥がれるため、40℃以下のぬるま湯に中性洗剤を溶かし、部品をつけ置きして優しく汚れを落としましょう。
徹底的にお掃除する場合は、取扱説明書を確認して、部品の破損や紛失に気を付けながらファンやフィルター、バッフル板、油受けなどを分解します。つけ置き後はスポンジで軽くこすり、水で洗剤をしっかりすすいでから、布巾で水気を拭き取り十分に乾燥させます。
レンジフードファンのお掃除方法は、以下でもご紹介しているのでぜひ参考にしてください。
レンジフードの効果的な掃除方法は?具体的な手順と注意点をご紹介
冷蔵庫

冷蔵庫のお掃除は、一つひとつ分けて進めると効率的です。まず運転を停止し、電源プラグを抜いてから中身を出し、不要な食品は処分しましょう。
冷蔵庫全体は、やわらかい布にぬるま湯を含ませ、固く絞ってから拭きとりましょう。棚やトレイ、引き出しも取り外してからふき取ることで普段のお掃除では見逃しやすい箇所も、きれいにすることができます。また、落ちにくい汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませふき取ります。最後に水拭きをし、水分が残っていたら乾いた布で仕上げます。
ドアパッキンや取っ手など、よく触る部分も忘れずに拭き取りましょう。冷蔵庫の裏や脚部にはホコリが溜まりやすいため、掃除機や乾いた布で年に一度は丁寧に除去しておくと、放熱効率が保たれ、省エネにもつながります。また製氷機は汚れやすいので、お掃除習慣がない方は、これを機に週1回のお掃除を習慣化すると良いでしょう。
冷蔵庫の製氷機のお掃除方法は、以下でご紹介しています。
製氷機はどのように掃除する?詳しい掃除方法やカビ防止策を徹底解説
浴室

浴室の大掃除では、日頃落としきれない浴室の頑固な汚れを集中的にお掃除します。
鏡のウロコ状の水アカには酸性洗剤やクエン酸が効果的です。クエン酸水(100mlの水に小さじ1/2のクエン酸)を鏡に吹きかけ、キッチンペーパーとラップで覆って数時間放置後、メラミンスポンジで優しくこすり、しっかりすすぎましょう。
また高温多湿な環境の浴室はカビが発生しやすいです。カビは黒カビと赤カビに分けられます。黒カビは水気を拭き取った後、塩素系漂白剤をかけて10分放置し、洗い流します。
赤カビはお風呂用洗剤をかけブラシでこすり、シャワーで流すか、重曹を粉末のままかけて落とす方法も有効です。 それぞれの汚れに合った洗剤を使い分けることで、浴室全体を清潔に保てます。
浴室のお掃除方法は以下の記事でもご紹介しています。
お風呂の掃除に便利な道具を紹介!効率よく掃除をしてキレイな浴室にしよう
洗濯機
洗濯機の大掃除では、ニオイや汚れを防ぎ清潔さを保てるよう、全体をしっかりとお手入れしましょう。まずは電源を切り、ドアは開けたまま乾燥させるのがカビ対策の基本です。洗濯槽は、専用の洗濯槽クリーナーを使って洗浄しましょう。ただし、ご自身で洗濯機の分解清掃を行うことは、ケガや故障のリスクがあるため、やめましょう。
洗剤投入口や糸くず・排水フィルターもお掃除しましょう。湿気がこもりやすいゴムパッキン部分も、見逃さず乾拭きするなどしてお掃除をすることでニオイやカビの発生を抑えられます。
さらに、裏や下のホコリにも注意が必要です。移動せずにお掃除できる範囲はホコリを取り除き、フィルターに溜まった汚れをお掃除することで、洗濯機の放熱性が高まり省エネにもつながります。
普段の使い方もひと工夫するとキレイを保てます。洗濯物は洗濯槽に放置せず、洗い終わったらすぐに取り出して乾燥させましょう。洗剤や柔軟剤は適量を守り、濃度や量を調整すると、洗濯機内部の汚れも抑えられます。
トイレ

トイレは日頃からお手入れをしているご家庭が多いでしょう。しかし、定期的にお掃除をしていても尿石汚れが目立ってしまうことがあります。日頃のお掃除でも落ちにくい尿石汚れには酸性洗剤が効果的です。ただし、塩素系洗剤と混ぜると有毒ガスが発生するため、絶対に併用せず、使用時は必ずゴム手袋を着用しましょう。
酸性洗剤は肌荒れ防止のためにも直接触れないようにします。 大掃除では便器だけでなく、換気扇のホコリ落としや、壁・床のお掃除も忘れずに行いましょう。壁や床には飛び散った汚れやホコリが蓄積しやすく、放置するとニオイやカビの原因になります。普段手が届きにくい部分まで丁寧に拭き掃除をし、トイレ全体を清潔に保ちましょう。
トイレのお掃除道具も、以下のコラムで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
トイレ掃除に役立つ掃除道具について解説
窓ガラス

窓ガラス掃除は、汚れや拭き残しが見やすい夕方や曇りの日がオススメです。日中の強い日差し下では汚れを見逃しやすく、拭きムラも発生しやすくなります。
軽い汚れなら、細かい繊維で汚れを吸着しやすい新聞紙が便利です。ぬらした新聞紙で全体を拭き、その後乾いた新聞紙で仕上げるとキレイになります。
汚れがひどい場合は重曹(皮脂汚れ向き)やクエン酸(水アカ向き)など、汚れに応じた洗剤を使い分けましょう。
お掃除は外側から始めるのがコツです。外側の方が汚れやすく、内側から始めると拭き残しに気付きにくくなります。
窓掃除のより詳しい解説は、こちらもご覧ください。
5分でできる!窓ガラスがキレイになる掃除方法を解説
床・フローリング

床やフローリングの大掃除では、掃除機やフローリングワイパーで乾拭きするだけでなく、よく絞った雑巾で水拭きして細かい汚れやホコリを取り除きましょう。水拭きは、乾拭きでは落としきれない皮脂汚れや細かいチリの除去に効果的です。
黒ずみの原因が、ワックスの劣化によるものであれば、専用のワックス剥がし剤で古いワックスを落とし、新しく塗り直します。
ただし、床材によって使用できる剥離剤やワックスの種類は異なるため、必ず事前に利用可能かを確認しましょう。仕上げにワックスを塗ることで、見た目が美しくなるだけでなく、汚れや傷から床を守る効果も期待できます。
床やフローリング掃除のより詳しい解説は、こちらもご覧ください
汚れをキレイに!フローリングの正しい掃除方法について解説
ベランダ
ベランダ掃除は、まず手すりや壁の汚れをぬらした雑巾や重曹水(手すりがアルミ製なら中性洗剤を推奨します)で落とし、床のゴミはほうきや掃除機で片づけます。
新聞紙を水でぬらして丸め、床にまいてほうきで掃けば、チリやホコリが湿った紙に吸着されて簡単に除去できます。特にマンションの水使用が難しい場合にオススメです。
排水口のゴミも古い歯ブラシなどでかき出しておきましょう。床の頑固な汚れには重曹水やクエン酸スプレー、デッキブラシでこすり、清掃後は十分に水拭きして仕上げます。
戸建てなど水洗いが可能な場合は、デッキブラシや中性洗剤で汚れを落とし、水で洗い流すのが効果的です。
大掃除を行うときに忘れがちな場所5選
「お掃除が必要な場所」というイメージが強い分、換気扇やトイレなどが大掃除のリストから漏れることは少ないでしょう。一方、次のような場所は大掃除の際に忘れがちなので、注意が必要です。
- 天井と壁の隅
- 窓のレール・サッシ
- 冷蔵庫の裏
- 家具の下や裏
- シンク下の収納
天井と壁の隅
リビングや家族の部屋などを大掃除する際は、床に目が行きがちです。しかし、天井と壁の隅も忘れずにお掃除しましょう。天井、壁の隅にはホコリが付着しています。ホコリを落としたときに床やテーブルを汚さないため、お掃除の際はあらかじめ新聞紙を敷いておきます。
ご自宅の室内で喫煙される方がいらっしゃる場合は、天井や壁にヤニ汚れが付いている可能性があります。ヤニ汚れは次の手順で落としていきます。
- 表面のホコリを落とす
- フローリングワイパーやハンディワイパーにドライシートを付けてヤニを拭く
- 中性洗剤を染み込ませた雑巾またはドライシートをフローリングワイパーやハンディワイパーに付けてヤニを拭く
- 水道水で湿らせてよく絞った雑巾をフローリングワイパーやハンディワイパーに付けてヤニを拭く
- ドライシートでヤニを乾拭きする
天井と壁の隅のお掃除に当たっては、先述した「高いところから低いところ」という手順を意識しましょう。
窓のレール・サッシ
窓のレールやサッシをお掃除する際は、次の手順で進めていきます。
| お掃除する箇所 | お掃除の手順 |
|---|---|
| レール |
|
| サッシ |
|
窓のレールやサッシをお掃除する際は、目線の角度を変えてみながら、汚れが残っていないかを入念にチェックしましょう。
冷蔵庫の裏
冷蔵庫の裏側も、ついついお掃除を見逃しがちな場所です。お掃除するには次のような方法で冷蔵庫を移動させましょう。
- 冷蔵庫の脚カバーを外す
- 冷蔵庫の左右にあるアジャスターをゆるめる(反時計周りに回す)
- 冷蔵庫を動かす
冷蔵庫は中身を減らすことで軽くなり、動かしやすくなります。また移動させるには力がいるため、怪我の予防という意味でも必ず2人以上で作業しましょう。
冷蔵庫の裏にはホコリが溜まっているため、クロスやハンディワイパーで取り除きます。コードや冷蔵庫の背面に付いた汚れは油分を含んでいるので、住宅用の中性洗剤を含んだクロスで拭いた後に、水拭きして洗剤を落とします。
家具の下や裏
冷蔵庫の裏側と同様に、家具の下や裏も忘れずにお掃除しましょう。家具の下や裏はホコリが溜まりやすくなっているにもかかわらず、掃除機のヘッドが届きにくいところも多いため、蓄積されたホコリが潜んでいるでしょう。
家具の下や裏をお掃除する際は、ハンディワイパーなど、細い隙間に差し込めるお掃除アイテムを活用します。より丁寧にお掃除するのであれば、家具の脚部分に新聞紙や雑誌を差し込むことで摩擦が減り、すっとスライドさせて動かすことが可能です。
家具に傷が付くのを防ぐことにもなるでしょう。タンスのように中身が入っている家具であれば、冷蔵庫と同様に中身をいったん空にすると軽くなり、より動かしやすくなるでしょう。
シンク下の収納
シンク下にある収納部分を大掃除する際は、収納している物を一度取り出します。その後、取り外せる部品があれば、取り外してシンク内で丸洗いしましょう。
収納部分にはゴミが溜まっているため、掃除機やモップで取り除いたら、中性洗剤を使って中の汚れを拭き取っていきます。
なおシンク下の収納部分からは、場合によってはカビたようなニオイがすることがあります。塩素系漂白剤を使ったお掃除が可能な素材であれば、次の手順でお掃除を進めましょう。
- キッチン(シンクのある場所)を換気する
- 収納している物を全て取り出す
- 塩素系漂白剤を付けた雑巾でシンク下を拭く(※)
- 未使用のキレイな雑巾でしっかりと水拭きする
- 水拭きした雑巾と異なる雑巾でさらに乾拭きする
- シンク下を開けたままにして乾燥させる
※塩素系漂白剤は効果が高い分、素材にも影響を及ぼしやすいです。塩素系漂白剤の使用が可能かどうか、各メーカーの取扱説明書などをよくご確認ください。
※塩素系漂白剤を使用する際は、肌に触れると荒れる原因となるため、必ずゴム手袋を着用してお使いください。
大掃除後の清潔を保つための習慣化のコツ

しっかり大掃除をしても、その後のお手入れを怠るとキレイな状態をキープすることはできません。大掃除直後の清潔な状態を保つためにも、日頃から以下のような習慣を心がけましょう。
週ごとの掃除スケジュールを作成する
汚れは放置すると落ちにくくなり、掃除時間も増えます。そのため日頃から小まめにお掃除すれば、簡単なお手入れでキレイを保てるようになります。
習慣化のコツは、曜日ごとにお掃除する場所を決めた「週ごとのスケジュール」を作ることです。例えば月曜はキッチン、火曜はリビングなどと割り振れば、自然にお掃除が日課になります。
特に力を入れるべきは、キッチン・風呂・トイレなどの水回りや、玄関、リビングといった汚れやすい場所です。
また週1〜2日は掃除場所を固定せず、気になる箇所を自由にお掃除する日にすると、漏れを防げます。スケジュールには場所だけを記載し、作業内容は細かく決め過ぎない方が長続きします。無理のない範囲で、休みも取り入れながら計画することが大切です。
1日5分の小掃除を取り入れる
毎日のお掃除を習慣化するには、各場所の作業時間を1日5分程度に区切るのが効果的です。短時間なら忙しい日や疲れている日でも続けやすく、身体的・精神的な負担を軽減できます。
つい夢中になって長くやり過ぎるのを防ぐために、キッチンタイマーやスマートフォンのタイマー機能を活用しましょう。お気に入りの曲を流しながら行えば、時間計測とモチベーションアップを同時にかなえられます。
5分でできるお掃除は意外と多く、例えばキッチンならレンジフードをさっと拭く、洗面所なら鏡を磨くなど、一箇所だけなら短時間で完了します。
「ながら掃除」もオススメで、階段を上りながら手すりを拭く、テレビを見ながらリモコンを拭くなど、日常の動作と組み合わせればストレスも感じにくくなります。
スムーズに始められるよう、掃除道具は手に取りやすい場所に置くこともポイントです。スタンド式ハンディワイパーやスティッククリーナーなどを掃除場所の近くに設置しておけば、隙間時間を活用して効率的にお掃除できます。
汚れが付く前に防止するアイテムを導入する
家をキレイな状態にキープするには、小まめにお掃除するだけでなく、未然に汚れを防ぐ対策を講じることも大切です。汚れを防止するアイテムは複数あるので、ニーズや目的に合ったものを選んで導入しましょう。
お掃除を楽にしてくれる汚れ防止アイテムには、さまざまな種類があります。以下ではお掃除する場所別にお役立ちアイテムの一例を紹介します。
【キッチン】
| 油はねガード |
|
| 撥水コーティング剤 |
|
【風呂場】
| カビ用のくん煙剤 |
|
| 撥水コーティング剤 |
|
【トイレ】
| 置き型洗剤 |
|
| すきまテープ |
|
| 汚れ防止パッド・シート |
|
【玄関】
| 撥水コーティング剤 |
|
| シューズボックスシート |
|
| 靴箱用除湿剤 |
|
収納を見直して整理整頓をキープする
収納や片付けがうまくいかないと物があふれやすくなります。改善の基本は3ステップです。
- 収納物を全て取り出す
- 使う物と使わない物を分ける
- 使いやすさを重視して収納する
まず物を全て出して、何がどのくらいあるかを把握します。仕分けでは、今後も使う物だけを残し、年1回も使わない物は処分するのがコツです。「将来使うかも」という基準ではなく、今の生活を基準に判断しましょう。
収納時は、頻繁に使う物を膝から上、あまり使わない物を膝から下に配置します。さらにカテゴリ別にまとめると探しやすくなります。例えば、リビングのチェストなら上段に家電系、次段に文房具など系統ごとに分けると出し入れもスムーズです。
作業が難しい場合は業者の力を借りる
年末は何かと忙しく、大掃除の時間を確保できないこともあります。そのようなときは、ハウスクリーニングなど業者の力を借りるのも一つの方法です。プロは業務用の道具や洗剤を使用し、頑固なカビや油汚れも効率的に除去できます。特にエアコン内部の清掃や大型家具・家電の移動を伴うお掃除など、自宅では難しい作業も安心して任せられます。
依頼は「大掃除の1日だけ」や「キッチンと浴室だけ」といった部分的な対応も可能です。料金やサービス内容は業者によって異なるため、複数社を比較して選びましょう。年末は予約が混み合うため、依頼は早めが安心です。
まとめ:大掃除は計画的に行いましょう!
大掃除は一年の汚れを落とし、新年を気持ちよく迎えるための大切な行事です。効率よく進めるには、事前にスケジュールやチェックリストを作成し、必要な道具・洗剤をそろえておくことが重要です。
大掃除後は週ごとのスケジュール決めや1日5分の小掃除、汚れ防止アイテムの活用で清潔を維持しましょう。
忙しく大掃除が難しい場合は、スポットでの家事代行サービスの活用も検討してみましょう。レンジフードファンの油汚れや鏡のウロコ取りなど、しつこい汚れのお掃除には、ハウスクリーニングの利用もオススメです。いろいろなサービスも活用しつつ、一年の汚れをしっかり落として気持ちよく新年を迎えましょう!
三菱電機のハウスクリーニングがオススメ!
- 家電製品を熟知したメーカーならではの清掃技術をご提供します。
- お客様の安心のため徹底教育されたスタッフがお伺いします。
- 家電のお困りごとやご相談にも丁寧にご対応いたします。
※サービス提供エリアに限ります。サービス詳細は下記リンクをご参照ください。
三菱電機の掃除代行がオススメ!
- 忙しいときや、来客前などの必要な時にお客様に代わって、掃除を行います。
- お掃除場所やサービス内容はお客様のご要望をお伺いします。
- 利用したい時にいつでもご利用いただけるプランもご用意しています。
※サービス提供エリアに限ります。サービス詳細は下記リンクをご参照ください。
#掃除 #清掃 #大掃除 #年末 #片付け #洗剤 #道具 #場所 #ポイント #コツ
-
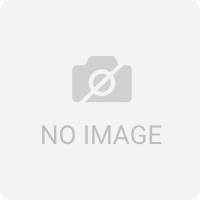
-
この記事を書いた人
くらトク編集担当